私、まるすけは昭和55年生まれの現在41歳(2021年9月5日現在)。
いわゆる「(昭和の)氷河期世代」というやつです。
以前「こんなに違う!昭和世代と平成世代の仕事の価値観」という記事でも書かせていただきましたが、日本が好景気に沸いたバブルというものを直接経験していないので、その時代を経験した先輩方とは色々とギャップを感じる事があります。
(もちろん私たちと今の20代の世代でも同じように価値観が違います)
そんな団塊の世代~バブル世代の諸先輩方との会話の中でよく聞かれるのが
「ビジネスシーンで使われていた死語」
ってやつです。
聞いてると、その当時の時代背景などが見えてきてこれが結構おもしろいんですよね(*^_^*)
そこで今回は、そんな
「今では使われなくなったオフィス死語」
を厳選して10個紹介していきたいと思います!
若い人も参考にしてみてくださいね!
半ドン

タイトルにも書いた「半ドン」
これは今でいう「午後半休」の意味。
私も小学生の頃はそうでしたが、1980年代頃まで土曜日は休日ではありませんでした。
午前中だけ授業をしてお昼に家に帰るという。
社会人も同じで、どの会社も普通にお昼まで仕事が行われていました。
そんな半日だけの日を表現する言葉として使われていたのが「半ドン」。
語源については諸説ありますが、オランダ語で「日曜日」を意味する「zondag(ゾンターク)」。
これが「ドンタク」となり、その半分という意味で「半ドン」となったという説が有力。
他には江戸時代、正午に鳴らした大砲の「ドーン」という音からついたなんていう説も。
私の職場の60代の職員さんも
「今日はお昼までの半ドンです」
って普通に使っています。
半ドンがわからない人多数なの😱
嘘でしょ…世代なの…🥺— るかるる (@luca_troll) September 3, 2021
ハナキン

漢字で書くと「花金」
週休二日制が浸透しはじめた1980年代後半。
それまで土曜日は仕事だったのが休日になった事で、金曜日の夜に遊ぶ会社員が増えていきます。
「翌日を気にせず、華々しく夜遊びできる曜日」
↓
「花の金曜日」
↓
「花金」
となったわけです。
今でも金曜日の夜が一番楽しいという方は多いのではないでしょうか♪
おわたよおわたよしごおわ!花金や(死語
— Kazue Kawabuchi (@kazueDEAF) September 3, 2021
(文σдσ)そういえばもう死語だけど、花金って言い出したの誰なんだろう…。メディア?
— 文色 (@airo_bot) September 3, 2021
おいくら万円

これは、正しい金額を冗談めかして伝える言い方。
たとえば、おつりが50円だとしたら
「はい、50万円!」
とか、飲み会など会費を聞く時に
「おいくら万円?」
とか。
あ、そういえば…( ゚Д゚)
私がまだ小学生の頃に駄菓子屋のおばちゃんがそんな風に言っていたような…。
「ほい!お釣り100万え~ん!」
って。
当時は何の事か分からずノーリアクションでしたが(笑)
ユニークなおばちゃんだったんですね~。
おいくら万円って死語なの……うそでしょ……
— 茉莉花 (@hitohabusi) July 18, 2017
え!?おいくら万円って死語なの!?
みんなも使うよね?ね!ね!ね!— B̈́́͑͗̈́͡ȁ̆̿͡t̛̓̚t̛̓̑̅͑̋ȅ̎̾̄͝r̛̉͂̐̒y̒̈͝🔋 (@t0120002222) August 16, 2020
ウチの大蔵大臣

若い人はまず「大蔵大臣」が何の事か分からないかもしれませんね(^-^;)
かつて日本には大蔵省という中央官庁がありました。
国家の財政を司る所ですね。
そんな大蔵省は2001年、中央省庁再編によって財務省と金融庁へと変わり、その姿を消しました。
つまり「ウチの大蔵大臣」という意味は
「財政の実験を握っている人=主婦や会社の経理担当者」という例え。
「この時の食事代が経費で落ちるかどうか、ウチの会社の大蔵大臣に聞いておいて」
とか
「今日の飲み会、参加したいけどウチの大蔵大臣が何て言うかなぁ…」
みたいに使ったそうです。
今も会計ソフトに「大蔵大臣」というものがありますよね。
若い人はそっちのイメージが強いかもしれません。
大蔵大臣とかもう死語なのでは
— たてぼう (@lllllT) September 26, 2017
もはや会計ソフト以外で耳にしなくなった半分死語の大蔵大臣
— 榊原 ユキヱ (@yukkie_0520) January 12, 2018
ドロン

ドローンじゃなく、ドロン。
これは「お先に失礼します」という意味。
よく忍者が姿をくらます時の効果音で使われていますよね。
アレを口に出して発していたのがこの「ドロン」という言葉。
忍者が消える時のように、手を組み合わせたポーズをして
「では、私はこれでドロンしま~す!」
という感じで使っていたそうです。
お仕事が終わったのでドロン(死語)します。
— 佳*佳 (@tensai_Okey) April 6, 2021
サテン

これは「喫茶店」を略した言い方。
「駅前のサテンで打ち合わせでもするか」
という感じで、当時はサラリーマンに限らず学生も使っていた言葉だそうです。
今なら「カフェ」ですかね。
ちなみに私はこの言葉、「今日から俺は!」のマンガで初めて目にしました。
あの作品の時代設定も1980年代なので、自然に使われていた言葉という事が分かりますね。
☕
Have a break ✨お気に入りのサテンで
キャラメルミルクティーでも
飲んで、くつろがない🐈?※ サテンて、死語 🙀? pic.twitter.com/8cXaigV9zw
— Kizu🐈living in Kagoshima 🇯🇵 (@Kizu_Kagoshima) May 22, 2021
写メ

「これもオフィス死語なの?」
と思わず驚いたのが「写メ」という言葉。
私が大学生だった2000年。
J-PHONE(現ソフトバンク)から、携帯カメラで撮った画像をメールで送受信できるというサービスが始まりました。
そのサービス名が「写メール」
すぐに大ブームになって他の携帯会社も同じようなサービスを開始しました。
その「写メール」を略して「写メ」と呼んでいましたね。
つい最近の言葉かと思っていましたが、すでに死語なんですね…(-_-;)
写メも死語なのか🥲
俺はもうこの世界では生きられないかもしれない— ゆい斗 (@yuito_cos) August 31, 2021
最近、写メという単語が死語になってることに時代を感じる。
— Kさん (@k3_funnylife) September 1, 2021
ガビーン

オフィス死語ではないかもしれませんが(^-^;)
がっかりした時や驚いた時に使う「ガーン」の事。
今でもマンガの効果音なんかで使われていますが、当時はこれを口に出して言っていたとか。
私の経験では、工場で働いていた時の50代パートさんで同じように「ガーン」という言葉を口に出して言う人がいました。
「マンガみたいだ(;゚Д゚)」
と思ったのをよく覚えています(笑)
死語一覧にガビーンが入ってた、ガッビーン
— 宇咲ゆずゆ (@candy_collet) September 3, 2021
社会の窓

私が小学生の頃、まだこの言葉は使っていた記憶がありますね。
どういう意味かと言うと
「男性のズボンのファスナー部分」
の事。
語源は1948年に放送されていたNHKのラジオ番組【インフォメーションアワー・社会の窓】から。
「社会の裏側に隠された部分を覗くと大事なものが見えてくる」という趣旨の社会派のトーク番組でした。
それをズボンのファスナーに例えた、という事ですね。
そんな意味も分からず、子供の頃は私も
「社会の窓あいてるぞ(=チャックあいてるぞ)」
とか言ってました(^-^;)
この前のイッテQで「社会の窓」が死語って言うのを知ってびっくりしたのをいま思い出した
— P0SEID0NJr (@POSEIDON1564) September 1, 2021
バタンキュー

この言葉は私も聞いた事があり、意味も知っていました。
倒れる音の「バタン」
意識を失う音の「キュー」
この2つが組み合わさり、疲れた時に布団に倒れてそのまま眠ってしまう様子を表現したのが「バタンキュー」という言葉。
「昨日も終電まで働いて、家に帰ってバタンキューだったよ」
という感じで使っていました。
なんか、響きだけ聞くとカワイイですけどね(^-^;)
昨夜はバタンキューが死語かどうか調べながらバタンキューした
— 原稿がんばるヘフ (@hefunonawa) September 1, 2021
おつかれさまでーす!
仕事終わったらもうバタンキュー(死語🤣)ですー。— れとごる (@retriever_Gol) September 2, 2021
まとめ
いかがでしたでしょうか。
これらの言葉を使っていた世代の人にしたら懐かしく思えたのではないでしょうか。
逆に若い人たちにとったら価値観や環境、時代背景そのものが違うので、かえって新鮮だったかもしれませんね。
そんな今の20代の人もやがて40代~60代と歳を重ねていき、いずれは逆の立場になります。
そうすると「今」使っている言葉が「死語」になります。
そうなった時に、そういう状況なんだという事をしっかり認識して
「なんですかその言葉…( ゚Д゚)」
とか言われないようにしたいものです。
…私も気を付けなくては(^-^;)
では、今回もお読みいただきありがとうございました_(._.)_
Follow @marusukepapa
![]()
にほんブログ村

人気ブログランキング











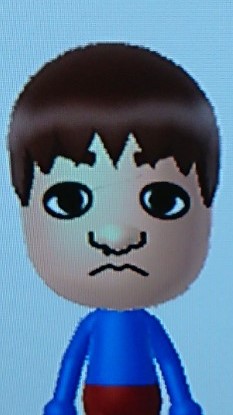
コメントを残す